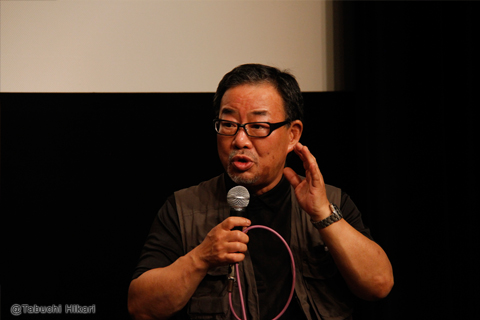講座レポート
災害をセルフする Q&A集
(※藤田直美君からは、まだ"返答"が届いてません。届きましたら追って掲載します。原一男記)
[討論](1)藤川佳三+藤川幸子+原一男(2)小林佐智子+原一男
【松江哲明】篇
今日は、強烈な個性の先輩たちに向かってひるまずに自分の意見をいっているのが印象的だった。松江さんをこの場に招いたことは講座を立体的なものにすることにつながったと思うし、この流れを次回以降も是非。発展させ、議論が白熱して行くことを楽しみにしています。
先輩たちを前にして、思いつくままの言葉を発していたことに「なんて恐ろしいことを」と思いもしましたが、僕が無邪気に意見をさせて頂けたのもドキュメンタリー監督たちの心の広さだと実感しています。アテネフランセで行われたシネマ塾の雰囲気が真剣勝負感に満ちていたことも大きいと思います。久々に味わう特別な空間でした。観客もぜひ遠慮なく討論に参加されることを期待します。
ただし、作品のテーマを聞くようなことは避けた方が良いと思います。なぜなら監督たちもそれを伝えるためにドキュメンタリーを製作している訳ではないからです。具体的な映像や、編集の繋ぎ、映っていたものに目を凝らし、そのディテールについて監督たちを問いつめて下さい。きっとその時、ドキュメンタリーの作り手にとっても「発見」が生まれることでしょう。
【森達也】篇
森監督の作品は、世界からほとんど「ヒステリー」に近い怒りをぶつけられる事が多いと思いますが、作品を発表した後に、「案の定」良識派がもしてきた時(ママ/意味不明)、どんな気持ちがしますか?やっぱり気持ちいいですか?
質問の意味がよくわかりません。罵倒されて気持ちいいわけないです。
映画の中で森監督がメインの登場人物になっていますが、森監督は撮られていることに対して、どれくらい意識的に「演じて」いたのでしょうか?
あなたは普段、どの程度意識して自分を演じていますか?両親の前。友人の前、恋人の前、それぞれ違うと思います。それはどのくらい意識的に演じていますか?そう訊かれて答えられるでしょうか。
4人の温度差や、立ち場や、考え方の違いが映画の中よりも、映画の外で強く感じてしまうが、一体誰が、この映画に責任を負っているのか。誰が答えを持っているのか、がわからない。(他の作品を言い訳にしてる?)
松林さんは「相馬看花」「祭の馬」を撮って、安岡さんは「遺言~原発さえなければ~」を編集している。でも森さんは「これ以上、語ることはできない」というようなことをおっしゃっている。それは本当でしょうか。本当だとすれば、何を語れたと考えておられるのか、本当に「後ろめたさ」しか語ることはないのか。逃げではないのか。自己矛盾はないのか。ここから進めていないということではないのか。いま、『311』と「3.11」に対して、どう捉えて、どう思っているのか。
映画に責任を持つことがアプリオリな前提になっているようですが、それは絶対なのでしょうか。
逃げではないのか。
逃げです。
自己矛盾はないのか。
あります。
ここから進めていないということではないのか。
そうです。
いま、『311』と「3.11」に対して、どう捉えて、どう思っているのか。
語る言葉はこれ以上ありません。
【安岡卓治】篇
「ヤマガタ」上映後のシンポジウムで、呉乙峰監督が自身の震災を撮ったドキュメンタリー『生命』の制作後、数年を経て精神疾患を発症したと語っていたが、『311』の制作が時を経て及ぼした影響を感じることはありませんか?
呉監督が、『生命』を作られた後、苦しい日々を経験されたことは、山形のシンポジウムでお聞きしました。
私も、『311』を作りながら、精神的に強いストレスを受けました。撮影された映像素材の総量は六十時間足らずなので、通常であれば2週間程度でラフ編集を上げられるはずなのですが、ひと月あまりも費やしてしまいました。他の業務と並行していたことも理由のひとつなのですが、素材を見るたびにひどく消耗するのです。
人の死を扱った映像が含まれる場合、私は精神的に参ってしまうことがありました。
『311』のメンバーのひとり綿井健陽が監督した『リトルバーズ イラク 戦火の家族たち』には、爆撃で亡くなられた犠牲者を収容するモルグの映像の他、バクダッドの病院の子供たちの映像が3時間近くもありました。
子供たちの映像がこたえました。
編集ができないのです。
編集という作業は、映像に目を凝らし、音声に耳をそばだてながら、どのフレーム(ビデオの場合1秒間に30枚のフレーム:静止画があります。)からその映像を使い始め、どのフレームで終わるかを決めて、ひとつひとつのショットを切り分けていく作業が基本です。
集中して映像と音声に向き合わなければならないのですが、子供たちが傷つき命を落としてゆく映像を見ていると、涙があふれてきて見続けることが出来なくなるのです。何度か編集を試みるのですが、見る度に思いが深まり、数秒見ただけで嗚咽するようになり作業になりませんでした。この場面を編集し終えたのは、半年余りにおよぶ編集期間の最終盤のことでした。
『311』の映像にも、ご遺体の一部が垣間見える場面がありますが、『リトルバーズ…』ほどの分量もありません。でも、現場では、石巻市大川小学校周辺で泥だらけのランドセルを見た時に動けなくなりました。そこにはご遺体はないのですが、森と綿井が撮った親御さんの証言に号泣してしまいました。
また、被災地の映像、これまで見たこともない破壊の規模の大きさに、どこをどう切り出してよいのか、逡巡が続きました。
素材と向き合うと、震災への恐怖と生命を奪われることの悲しみが襲ってきます。
編集室では、時間の流れが止まってました。
私たちが被災地を訪れた3月のままです。
外では桜が咲き誇り、やがて力のある新緑が育ち、梅雨の雨が滴っているのに、編集室の中は、刺すような寒風がふきすさぶ3月の被災地のままです。
来る日も来る日もその映像を見つめ、なすすべを見失って時間が過ぎてゆきました。
『311』で編集上外すべきだったかもしれない「卒業式」のシーン。泣きながら組みました。「勇気を翼にかえて、希望の風にのり…」という唱歌のフレーズに支えられながら編集しました。
数年後の変化についてお尋ねでしたね。
森は、あの時の「うしろめたさ」を抱えたまま、執筆や講演活動を続けています。
松林は、「相馬看花」、「祭の馬」の2作品を作りました。
綿井は、イラクに赴き、イラク戦争の10年を描く活動を続けています。
そして、私は、今年3月に公開した『遺言 原発さえなければ』をはじめ、震災を描いた3作を仕上げ、今、4作目が完成しようとしています。まだ、これからも取り組みは続けるつもりです。
それぞれが、この『311』に導かれ、それぞれの活動を続けているように思います。
編集は安岡さんがメインだと伺いましたが、作品完成後には、他の3人から、このシーンは入れて欲しい(欲しくない)という箇所があったら教えてください。
編集は、安岡が担当しました。
5月の初旬にラフ編集をみんなで見ました。
みんなから様々な提案がありました。
これを足して欲しい、これを抜いて欲しい、様々ありました。希望の通り作業したところもあればそうしなかったところもあります。私自身、みんなと見直して「足そう」「抜こう」と思ったところがあります。4人がそろったところで確認しないと、正確なことが申し上げられません。
悪しからず。
何故か『イージーライダー』を想い出してしまいました。けっこうヘビー級なのに、考えるに、保守的なものの返り討ちかな?と想えます。本作で森監督、安岡監督の保守観は変わったのでしょうか?
ラストカットは、加藤泰監督へのオマージュでしょうか?
「保守的なものの返り討ちかな?」というご質問、趣旨がいまひとつ掴めないのですが、震災という題材がこれまでそれぞれの中にあった社会観や映画観を脅かしたり、覆したりしたことはあったと思います。
社会への批評性豊かな論評を発表してきた森の姿勢は、震災後も揺るぎないように見えますが、彼の視点の軸になる「社会」と「個」の距離感が微妙に変化してきたのではないかと思っています。これは、安岡が感じた印象に過ぎないのですが。
シネマ塾の話の中でも頻繁に出てきた、「うしろめたさ」という森のフレーズは、今回の『311』を経験したことで鮮明になってきたのではないでしょうか。だからこそ、腹をくくって、心を鬼にして、伝えようとする力を授かったのかもしれません。それは、自然という圧倒的な力の前で、人間がいかにあるべきかという大きな命題を突き付けられたからだと思います。社会の構造にある「保守」とか「革新」とか、そんな単純な二項対立構造の文脈に陥ることの無意味さ、逆に言えば人間とは何かという根源的な問いに向かう必然性を突きつけられていると思います。
「加藤泰監督へのオマージュ?」
ちょっとうれしいですね。映画を作る、ということは自分が見た映画への恩返し(オマージュ)だったり、リベンジだったりすると思っています。先人が作られた数々の作品を経験しながら、自らの作法を模索しているからです。
意識的であったかどうかは別にして、そういった先人の作品に使われた技法を引用することもありますが、常に独自性を追求しなければならないと思っています。
寄り添いドキュメンタリーは何故、生まれるのか?そんなに簡単に寄り添えるのか? 以下、判読不能。
震災後作られたドキュメンタリーの多くが、そう呼ばれてもおかしくないかもしれません。
被災した人を助けたい、少しでも力になりたい。
そう思うことは人間として自然なことだと思います。実際、支援活動と並行して作品づくりを続けられている方々も大勢いらっしゃると思います。「うしろめたさ」をそれで少しでも解消したいという思いも理解できます。
が、私は取材者はあくまでも非当事者であるべきだと思っています。
その出来事を、その出来事で苦しんでいる人々をキャメラを携えた非当事者として見つめ、独自の視点で伝えてゆくかを追求しなければならないのだと思います。
だから、森が様々な場で伝えてきたように「うしろめたさ」を抱き続けることが大切なのだと思います。
もちろん、私のように映像を見つめる編集という仕事を続けていると、いつの間にか、映像の中に入り込んでしまうことが多々あります。その場にいるような、その場の人々の感情を共有する意識がないと、映像を切れないこともあります。自分のいる場所を見失いかけることがあるのです。でも、そこから立ち戻り、作品の世界を構築しない限り、映画は生まれないのではないかと思います。
ラストで4人が歩いていくカットは、やらせっぽいカットでしたが、誰の発案で、誰が撮ったのか? このカットに関しては議論にならなかったのかを知りたいです。
ラストショットは、松林要樹が撮影したものです。他の四人は撮影されたことをはっきり自覚していません。
四人は、森、綿井、私と共同通信の田平さんなのですが、映像では、松林を含んだ四人に見えると思います。
私たちは、撮影期間中、みんなでひとつの作品を造るなどという意思はありませんでしたから、どこで何を撮るかは、四人各自の判断でした。
フィックスで夕日を背景にした広角の映像は、この作品の中では明らかに異質です。その異質さ、そして、「四人が去っていく」という構図から、その作品のラストに選びました。「多義的」な投げかけで終わりたかったからです。
編集過程で何度か四人でチェック試写をしましたが、このラストへの異議はありませんでした。
松林は少し照れていたようでしたが、嬉しそうでした。
「え? 何これ?」とお感じになったとしたら、こちらの意図の通りです。見終わってスンナリ納得されたらたまりません。そんな映画でいいと思っています。